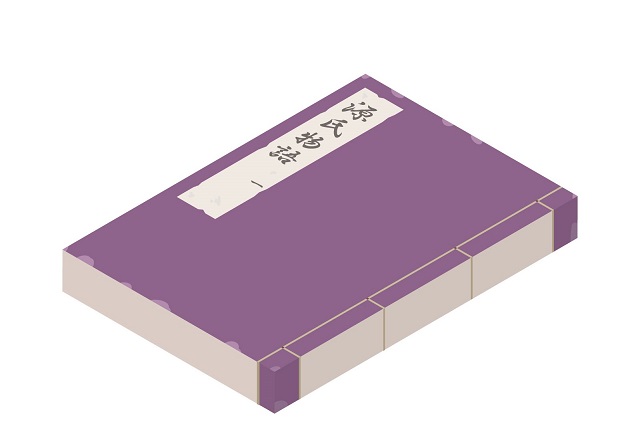【第6帖】末摘花(すえつむはな)【源氏物語あらすじ・解説】
光源氏18歳の正月ごろから19歳の正月ごろまでのお話。
時期的に「若紫巻」とかぶっています。
「末摘花(すえつむはな)」と出会う経緯や、彼女を源氏がどう思っているかが事細かに描かれています。
対訳にはなっていないのでご注意ください。
登場人物(回想含む)
光源氏、夕顔、左大臣家にいる夫人、六条の貴女、空蝉、軒端の荻、大輔の命婦、常陸宮の女王(末摘花)、頭中将、若紫
あらすじ
夕顔(ゆうがお)を失った悲しみを、年が変わっても源氏は忘れることが出来ずにいた。
左大臣家にいる夫人からも、六条にいる貴女からも、夕顔のように自由で気楽な心持ちは得られるものでなない。
色々な女性に文を送ってみるが、どれもこれといって心が動かず上手くもいかない。
空蝉(うつせみ)や軒端の荻(のきばのおぎ)が思い出される。
源氏は一度関係を持った女性を忘れ去る性質ではなかった。
左衛門の乳母の一人娘で、御所に仕えている大輔の命婦というものがいる。その者から聞いた話で、常陸宮が年をとってからできた娘がひとり孤児になっているらしい。
気の毒に思い、源氏は命婦に詳しく話を聞いてみた。どうやらおとなしい女性で、琴をよく弾いているようだ。
源氏はその琴の音を聞いてみたいと思った。
十六夜の朧月の夜に、命婦を頼りに源氏はその琴の音を聞くことができた。命婦が女王に弾いてもらうよう頼み、離れた命婦の部屋でその音を聞いたのである。
命婦は女王にあまり長く琴を弾かせるつもりはなかったので、早々に退出して源氏のいる部屋に戻ってきた。
源氏は命婦に、もっと女王に近づきたいと頼み、庭に出た。庭も邸内も荒れた様子である。
と、庭に男がひとり立っているのが見えた。
源氏をこっそり付けてきたきた頭中将であった。源氏は安心もし、またおかしくもなった。
ふたりはひとつの車にいっしょに乗って、左大臣家へと帰った。
源氏は常陸宮の女王に手紙を送っていたが、返事は来なかった。なんと頭中将も送っていたらしく、同じく返事は来ていないらしい。
大輔の命婦に源氏は仲介を頼むが、命婦はあまり乗り気ではない様子で、月日だけが経って行った。
春が過ぎ夏が過ぎ、秋になっても手紙の返事をもらえていない。こうなると源氏も意地というものが出てくる。
命婦もだんだんと考えが変わり、少しふたりを物越しに会わせてみようかという気になっていた。
八月の二十日過ぎ、命婦はふたりを物越しに引き合わせることにした。女王は恥ずかしがっている様子であった。
命婦は物越しにちょっと会わせるだけのつもりであったのだが、源氏は女王の態度に口惜しいものを感じ、そのまま結婚してしまった。
ただ、新しく愛情が湧いてくる、という感じでもなく、女王の様子に少し腑に落ちないものも感じていた。
だが女王の身分を考えると、一度きりの関係で終わらせるわけにはいかない相手である。
静かに二条院へと源氏は帰り、煩悶しながら又寝をしていると、頭中将が訪ねてきたのでいっしょに御所へ行き、その日は終日宮中で仕事をした。
本来なら朝早くに後朝の文を出し、二日目の晩も続けて新妻のもとへと通うのが礼儀である。しかし源氏はそうしなかった。文を出したのも夕方になってやっとである。
源氏の心をひくものが、女王には見いだせなかったのである。ただ、いつまでも捨てずに愛していこうとは源氏は思っていた。
九月になって、出仕してきた命婦に女王の様子を源氏は尋ね、その後ときどき常陸宮へ通ったものの、外へ通うことがおっくうにもなっていた。
若紫を二条院に迎えたこともあり、六条の貴女にもあまり通わなくなっていた時期でもあった。
源氏はいまだに女王の顔を見ていない。手探りに少し不審な点を感じ、顔を見てみたいとは思うし、見れば愛情がわくこともある。でも見るのが不安でもあった。
夜にこっそりのぞいてみたが、女王の姿が見えるはずもなく、女房たちのあまり趣味の良くない出で立ちが見えるだけであった。
女王のもとを訪れた翌朝は雪が美しかった。いっしょに雪を眺めようと源氏は女王を促し、内気ながらも素直な女王は姿を見せた。ついそちらの方へ目をやった源氏は、その容貌にはっとした。
とりわけ鼻が長く先が赤いことに目が行った。顔色は白く青みがかっていて、面長に過ぎる痩せ気味の女王。頭の形と髪のかかり具合は良いが、額は高く、服装もいまいち。歌を詠みかけても返歌も出てきそうにない様子である。
源氏は女王をあわれに思い、自分以外の男にはこの女をずっと妻としておくことは出来ないだろうと思った。
源氏は女王に絹などを贈り、老いた女房たち、門番の者たちにも贈り物をし、生活費も与えた。自尊心のある女ならば耐え難いことであるが、それらを女王は素直に喜んで受け取ったので源氏も安心した。
その年の暮れ、大輔の命婦が源氏のもとにやってきた。女王からの手紙と贈り物を源氏に届けに来たのだ。
手紙も贈り物も、ひどく趣味の悪いものであった。
源氏はこっそりと
なつかしき色ともなしに何にこの末摘花を袖に触れけん
と書き、それを見た命婦は
くれなゐのひとはな衣うすくともひたすら朽たす名をし立てずば
と詠んだ。
源氏が実際に女王に送った手紙はまた違ったものであったが、それにも「赤い花の歌」が詠まれていたので、それを見た命婦はおかしくて笑ってしまった。
元三日が過ぎ、今年はまた男踏歌(おとこどうか)がある年である。にぎやかな様子に寂しい常陸宮を思い、七日の白馬(あおうま)の節会(せちえ)が済んでから、源氏は常陸宮の女王たる末摘花(すえつむはな)のもとへ向かった。
翌朝見た末摘花は、頭の形や髪なども美しく、源氏の贈った衣などで現代風にもなっていた。そして初めてその声を、源氏は聞くことができた。
別れ際に見えた赤い鼻だけが残念だった。
二条院に帰った源氏は、若紫と絵を描いたりなどして遊びながら、絵の中の人の鼻の先を赤く塗ってみた。自分の鼻も赤く塗って見せると、若紫はおかしがって笑うのであった。
源氏は若紫に「墨を塗ってはいけませんよ、赤いのはまだ我慢できますよ」と言っている。
このようにふざけあう二人の姿は若々しく美しく見えるのであった。
補足
末摘花の物語は、蓬生巻にも描かれています。